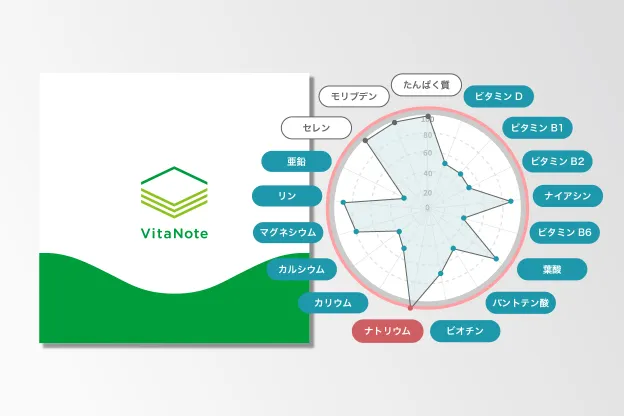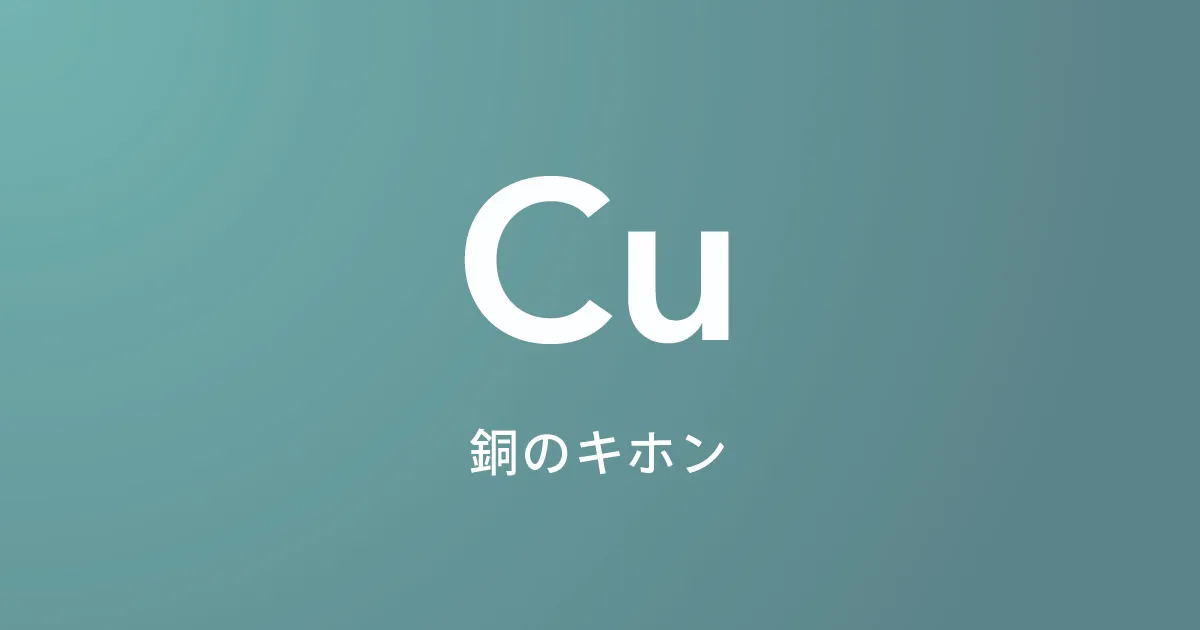
目次
銅の機能
銅の消化、吸収、代謝
銅の摂取量
過不足のリスク
銅が多く含まれる食品10品目
原子番号29の遷移金属元素です。
成人の場合体内に約100mg存在し、そのうち約65%は筋肉や骨に含まれています。3)
金属ミネラルの中でも毒性が低く、沢山摂っても排泄されやすい栄養素です。1)
銅の機能 1)
鉄の働きをサポートする
血液中の銅のほとんどはたんぱく質と結合して「セルロプラスミン」という酵素たんぱく質を作っています。
セルロプラスミンは鉄の代謝に働き、鉄の吸収・貯蔵、赤血球の成分であるヘモグロビンの合成に関わります。
活性酸素を除去する
赤血球中の銅のほとんどはスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)という酵素に存在します。
SODは活性酸素を分解する働きがあり、動脈硬化や糖尿病の進行を予防すると考えられます。
銅の消化・吸収・代謝 2)3)
小腸で吸収され、吸収率は60%程度
ほとんどの銅は小腸で吸収され、肝臓に貯蔵されます。
肝臓でたんぱく質と結合してセルロプラスミンとなり、各組織へ運ばれて行きます。
ほとんどの銅は胆汁と一緒に小腸に分泌され、便に混じって排泄されます。
吸収率は60%程度だと考えられています。
銅の摂取量 3)

成人の男女で、0.7〜0.9mg/日摂取が推奨量とされています。
耐容上限量が定められています。
過不足のリスク 1)3)
通常の食事による過剰症の心配はない
多量に摂取した場合も排泄されるため、一部の遺伝的疾患を除き、通常の食事で過剰症になる心配は基本的にありません。
ただ、銅サプリメントの使用が死亡率を上昇させるという研究もあり、アメリカ・カナダの食事摂取基準をもとに耐用上限量が設定されています。
サプリなど健康食品の使用による健康への影響は、まだ情報収集段階です。
推奨量を大きく超えた銅の摂取は控えた方がよさそうです。
欠乏症は起こりにくいが、貧血のリスクがある
健康で通常の食事を摂取できていれば、欠乏症が出ることはありません。
不足すると、鉄が十分でもヘモグロビンが作られないため貧血になります。
他にも骨がもろくなったり、髪の色素が抜けたりすることがあります。
銅が多く含まれる食品 1)4)
レバーや魚介類に多く含まれています。
様々な食品に含まれるため、特に意識しなくても不足や摂りすぎの心配はあまりありません。
参考文献
- 上西一弘. 栄養素の通になる. 第4版, 女子栄養大学出版部, 2016, p.208-211.
- 奥恒行, 柴田克己. 基礎栄養学. 改訂第5版, 南江堂, 2015, p.212-214.
- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2020年版.
- 文部科学省. 日本食品標準成分表2020年版(八訂).
- 厚生労働省. ”untitled”. https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0529-4aj.pdf(参照 2024-05-15)